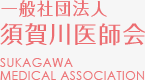医師会について
須賀川医師会ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
2025年6月から國分啓二前会長の後任として、須賀川医師会会長に就任いたしました。本会は、須賀川市、鏡石町、天栄村の3市町村の医師会員からなり、2025年度現在、会員数97名、6病院、48診療所から構成されております。診療圏は3市町村を中心に、石川郡、矢吹町に及び圏内人口は約14.7万人になります。日頃はかかりつけ医として地域住民の健康を守り、必要であれば病院の先生方へ紹介し専門的な診療を行っております。病院での治療が終了した場合は、再度かかりつけ医が診療するか、リハビリ専門の病院等に転院することもあり、通院が困難な場合は、自宅や施設での在宅医療に移行する場合もあります。特に在宅医療では、介護や福祉、行政などの多職種との連携が大切であり、後方病院との連携も行っております。これからも地域の皆様の健康を守り、地域全体の医療・介護・福祉の充実を目指して活動したいと思います。
医師会では、現在次のような活動を行っております。
1.須賀川市休日夜間急病診療所:年間を通じ一次救急診療を実施、
二次救急病院と連携しています。
2.須賀川市在宅医療・介護連携拠点センター:自宅で医療や介護が必要となる
場合の相談窓口で、専門の相談員が医療や介護の専門職へ連絡をとります。
3.産業保健活動:産業保健センターでの活動。事業所等の産業医活動。
4.学校医:地域内の小学校・中学校・高等学校での健診、健康相談
5.介護認定審査員:介護認定作業の円滑な運営
6.特定健診、がん検診:各市町村からの受託事業
7.予防接種:各市町村からの受託事業
8.市民公開講座:地域住民に対しての医学知識の向上と普及
9.研修会・学術講演会:医療従事者のスキルアップ
これからは医療の専門職である、歯科医師や薬剤師の方々との連携も深めて、在宅での口腔ケアや服薬指導の取り組みも大切になります。また各医療機関内での診療の充実は勿論のこと、地域住民の生活の場での健康管理、診療もますます重要になっております。訪問診療などの体制を充実させ、介護や福祉、行政の皆さんとの連携を更に強化し、超高齢社会を迎えている地域の皆様が安心して生活できる地域づくり、まちづくりを目指します。
このホームページが地域の皆様のお役に立てることを切に願っております。
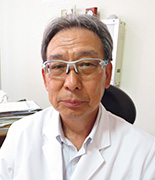
塩田 康二
| 昭和29年 | 岩瀬郡医師会と称し、事務所を須賀川市菊阿弥に置く |
|---|---|
| 昭和30年 | 岩瀬郡医師会を須賀川医師会と改めた |
| 平成20年 | 9月須賀川医師会館を竣工 |
| 【歴代会長】 | |
| 初代 | 菊池源造(昭和22年4月~昭和42年3月) |
|---|---|
| 2代 | 鶴島 孝(昭和42年4月~昭和51年8月) |
| 3代 | 豊増豪亮(昭和51年9月~昭和53年4月) |
| 4代 | 矢部研也(昭和53年4月~平成2年3月) |
| 5代 | 大河原清(平成2年4月~同年8月) |
| 6代 | 矢部研也(平成2年8月~平成4年3月) |
| 7代 | 本田和正(平成4年4月~平成8年3月) |
| 8代 | 野崎 央(平成8年4月~平成12年3月) |
| 9代 | 長谷部邦義(平成12年4月~平成14年3月) |
| 10代 | 春日 明(平成14年4月~平成20年3月) |
| 11代 | 黒澤三良(平成20年4月~平成24年3月) |
| 12代 | 西間木友衛(平成24年4月~平成27年6月) |
| 13代 | 髙橋清二(平成27年6月~令和元年6月) |
| 14代 | 國分啓二(令和元年6月~令和7年6月) |
| 15代 | 塩田康二(令和7年6月~現在) |
| 所在地 | 〒962-0848
福島県須賀川市弘法坦19 TEL 0248-73-3723 FAX 0248-73-3405 |
|---|---|
| 会員数 | 104名 (令和元年6月現在) |

| 役職&委員会 | 役員・委員氏名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 顧問 | 西間木 友衛 | 髙橋 清二 | |||
| 理事&担当 | 会長 | 塩田 康二 | |||
| 副会長 | 大谷 弘 | 矢部 順一 | |||
| 委員会 | 委員長 | 委員 | |||
| 医療保険指導・労災・医事紛争 | 塩田 康二 | 渡辺 行彦 | 國分 啓二 | ||
| 介護・福祉・精神保健 | 矢部 順一 | 熊谷 ユキ絵 | 関根 健司 | ||
| 産業保健 | 熊谷 ユキ絵 | 圓谷 昭市 | 池田 史仁 | 三浦 純一 | |
| 会報・広報・デジタル化 | 後藤 淳 | 石井 勉 | 矢部 順一 | ||
| 勤務医・労働安全・医療安全 | 大谷 弘 | 津田 謙矢 | 石井 勉 | 池田 史仁 | |
| がん検診・がん対策 | 石川 秀雅 | 池田 史仁 | 矢部 順一 | ||
| 特定健診・生活習慣病対策 | 矢部 順一 | 関根 健司 | 太田 昌宏 | 渡部 徹 | |
| 学術・生涯教育 | 太田 昌宏 | 大谷 弘 | 熊谷 ユキ絵 | ||
| 乳幼児健診・予防接種・学校保健 | 石井 勉 | 渡辺 行彦 | |||
| 地域医療・救急医療・休日夜間診療所 | 渡辺 行彦 | 津田 謙矢 | 佐藤 晃一 | 後藤 淳 | |
| 地域包括ケア・在宅医療 | 関根 健司 | 後藤 淳 | 矢部 順一 | 三浦 純一 | |
| 感染症(コロナ感染)・災害対策 | 佐藤 晃一 | 石川 秀雅 | 圓谷 昭市 | 渡部 徹 | |
| 監事 | 大越 透 | 渡辺 裕子 | |||
| 議長 | 小橋 主税 | ||||
| 副議長 | 渡辺 英裕 | ||||
| 裁定委員 | 吾妻 耕治 | 黒澤 三良 | 圓谷 幸雄 | 神山 修 | |
| 山田 善夫 | |||||
| 医療連携・感染症対策委員会 |
|---|
|
病原性の高い感染症によるパンデミックが懸念されていますが、可能性が高いものとして新型インフルエンザがあります。
その脅威から皆さんの生命と健康を守り、生活や経済に及ぼす影響を最小にすることが必要です。 緊急事態宣言が発令された際には、県や市の対策本部・県中保健所・薬剤師会・中核医療機関・消防などの関係者と我々医師会も密接に連携を図り、実情に応じた医療体制の整備を推進するために重要な役割を果たさなければなりません。 |
| 学術・生涯教育委員会 |
|---|
|
1. 須賀川医師会会員の日常診療の質をさらに向上させるため、福島県医師会、日本医師会とも連携し、生涯教育に力を注いでいます。
学術講演会、研修会、症例検討会などを市内の病院や須賀川薬剤師会とも連携し行っています。 2. 地域住民に対して各種疾病、医療、予防医学介護福祉等について啓蒙を行うため市民公開講座などを開催しています。 |
| 胃がん・大腸がん検診委員会 |
|---|
|
高齢化及び食生活の欧米化の影響で、胃がん・大腸がんは増加傾向にあります。
現在胃がん・大腸がん検診は、40歳以上を対象に行われており、須賀川地域は検診によって毎年胃がん、大腸がん共に約10名前後の方が発見されております。 日本人の胃がん死亡数は毎年男性約3万人、女性約1万8千人前後とあまり増減していませんが、胃がんになる人の数は、徐々に増えています。 つまり胃がんになっても、完治する人が多いため、死亡する人はあまり増加していません。これは、日本における胃がん早期発見・早期治療の進歩が著しい証拠と考えられます。 以前よりの集団検診に加え施設検診を開始してから、受診者の希望によりX 線検査、内視鏡検査を選択でき、検査を希望日に合わせて受けることもでき、受診者の利便性が高くなり、受診者数も増加し、内視鏡検査なら小さい病変の発見・同時生検による確定診断まで1回の検査で行うことができ、胃がん検診の定期的な受診が、胃がんの早期発見につながり、胃がん死予防に役立っていると思われます。 大腸がんに関しては、女性では部位別死亡者数の第1位、男性では第3位です。大腸がんにかかる方の割合は、50歳代から増加し始め、高齢になるほど高くなります。 しかし、早期に発見すれば、内視鏡的切除などで完全に治すことができます。 受診数の増加を図り、この1次検診で便潜血反応をチェックし、陽性者を2次検診として大腸ファイバー及び注腸レントゲン検査を行い病変の早期発見に努めております。 対策委員会としては検診に携わる先生方の要望や課題などに取り組みながら、専門医を招いて講習会、症例検討会などを開催しており、より精度を高め、より意義ある検診を行っていきたいと思っております。 |
| 休日夜間診療所運営委員会 |
|---|
|
須賀川医師会では薬剤師会のご協力のもと須賀川地方休日夜間急病診療所の診療を365日行っています。 応急的な診療に限られますので血液検査・各種注射・外傷の処置などはできませんが、須賀川市・鏡石町・天栄村のほか近隣地域から毎年2500人以上の方が受診されます。インフルエンザ流行期など受診者数が増大する時期には医師を2人体制にして待ち時間の短縮を図るなど受診しやすい診療体制づくりをしています。 |
| 学校保健委員会 |
|---|
| 現在学校医として数多くの先生方が活躍され、学校健診などを通して教職員の方と連携を深めながら子供たちの疾患の予防や早期発見に努めています。これまでも感染予防や食物アレルギーの問題などに対処してきましたが、子供たちの運動不足による運動能力の低下や過剰な運動によるスポーツ障害が深刻になってきており平成28年度から学校健診に運動器健診が組み込まれました。さらに福島県では震災・原発事故の影響から肥満症の子供が増加しており、肥満を持つ子供たちの生活・運動・食事指導にも力が注がれています。 |
| 医事紛争・災害対策委員会 |
|---|
|
当委員会の活動としましては、災害対策につきまして、平成23年3月11日の東日本大震災を踏まえ、今後予想される様々な自然災害に対して、当医師会としても組織としての対応が必要とされますことから、災害対策本部と連絡体制網を作り対応して行きたいと考え、立ち上げました。
地域住民の生命・健康維持に対処するため、会員先生方にはご協力よろしくお願いいたします。具体的な活動内容は、対策会議にて検討しております。 また、災害時に須賀川医師会会員と識別できるようユニフォームを作成しております。 |
| 在宅医療委員会 |
|---|
|
平成24年度から在宅医療連携委員会担当理事を務めております矢部順一です。
委員長の関根健司先生、副委員長の山田善夫先生と協力し、活動しております。 地域社会の過疎化や少子高齢化、さらに病院勤務医不足等により、今後ますます在宅医療のニーズは高まってくるものと考えられます。 しかし、現在の当地域の在宅医療は、それぞれの先生方の個別のご努力に頼っている状況で、組織的な体制が構築されているとはいえません。 当委員会では、安定的な在宅医療を継続して行くために、在宅医療を行う医師同士の連携、緊急時の入院医療機関との連携、さらに訪問看護をはじめとする介護関係機関との連携強化等を目的に活動しております。 患者さんやご家族が、安心して在宅医療を受けられるような体制を作っていきたいと思います。 皆様には今後ともご指導ご協力をよろしくお願いします。 |
| 予防接種・乳幼児健診委員会 |
|---|
|
【予防接種】
ワクチンで防げる病気から、子供たちを守るため予防接種を受けましょう。 【定期接種】 接種年齢などが法で定められており、無料で受けられます。県内の市町村と医師会との委託契約により、指定医療機関で接種できます。 三種・四種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、BCG、麻しん・風しん混合、不活化ポリオ、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん、高齢者のインフルエンザ。 詳細は市の健康づくり課へお問い合わせください。 【任意接種】 接種する義務はなく有料となりますが、大切な予防接種です。 B型肝炎、ロタ、水痘、おたふくかぜ、インフルエンザ。 【小児保健】 乳幼児の健康診査では身体計測と診察を行い、発育が順調か、病気がないかどうかなどを確認します。 3・4ヶ月児健診、9・10ヶ月児健診、1歳6ヶ月児健診、3歳児健診がそれぞれ年16~18回行われます。 詳細は市の健康づくり課へお問い合わせください。 |
| 産業保健委員会 |
|---|
|
昨今の企業を取り巻く労働環境は大きく変化し、過大なストレスとともに健康障害を患う労働者が急増。
過重労働対策・過労死や過労自殺といった問題・メンタルヘルスの問題と医師の関わるべき産業保健活動の重要性は増すばかりです。 ①委員会の構成は主に認定産業医よりなります ②産業医の資質向上と地域保健活動の一環である産業医活動の推進を図るために、年1ないし2回産業医学研修会を開催しています。 ③50人未満の企業に対しては、福島県須賀川地域産業保健センター(須賀川医師会館内にあります)と協同して、個別訪問・健康相談窓口・メンタルヘルス相談窓口等を介して、産業保健活動を行っております。 |